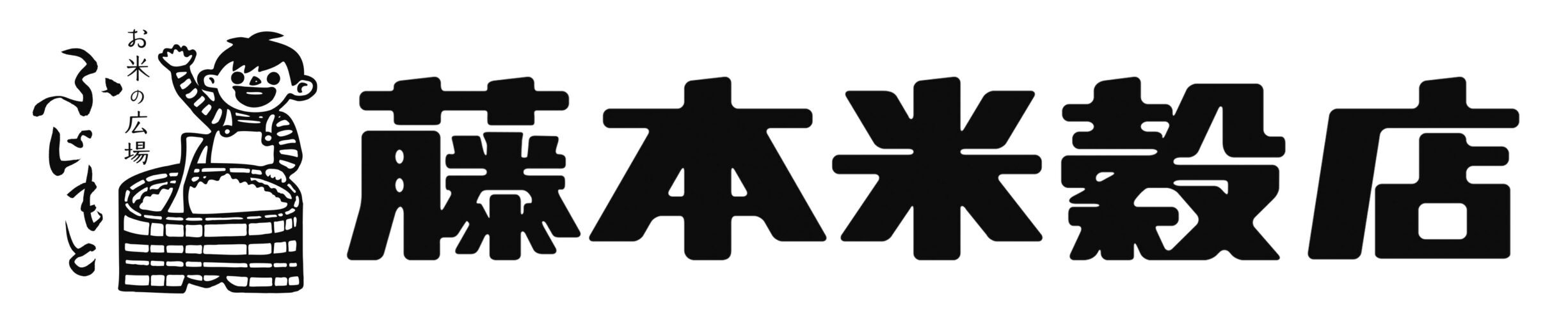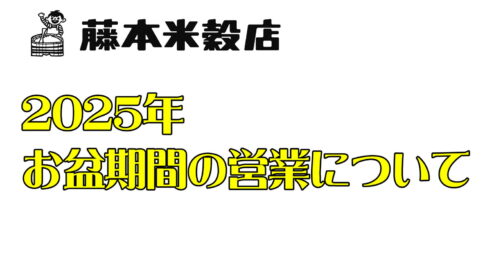山陰中央新報社さん発行の山陰経済誌「山陰経済ウィークリー」に掲載頂きました。
「さんいん企業物語」というコーナーで、4週連続掲載のものです。



以下、内容を転載します。
【企業物語】藤本米穀店(2)「生産者との絆」
栽培法や風土に触れ農家と交流
有機研究会結成し上質品追求も
第2次世界大戦の戦時統制で1942(昭和17)年に食糧営団に吸収された藤本米穀店だったが、終戦から14年後の59(同34)年に新たな体制での再スタートを切った。配給業務などに奔走してきた2代目の藤本幸市郎は、当時は松江市議会議員としての活動を精力的に行っており、再スタート後の店を長男の藤本淳一に託すことを決め、淳一が3代目として運営を担った。
食糧管理法の時代に
その後、78(同53)年3月には、淳一の長男で現在、(有)藤本米穀店(松江市東本町、藤本真由社長)の会長を務める真一郎(63)が島根大学農学部の卒業を迎え、淳一からの強い要請もあって同年4月に藤本米穀店に入ることを決めた。家業である商売の世界に入った真一郎は、父親の指導を受けながら配達や精米など全般の業務に精力的に当たっていった。
真一郎が仕事を始めた頃は食糧管理法があり、農家から直接コメを買うことができない時代だった。当時、藤本米穀店も県内産のコメを仕入れるのは卸業者からだった。それだけに販売する立場の業者が生産地を訪れることには意味がないようにも考えられたが、真一郎は違った。
仕入れたコメを対象に、真一郎は生産者である農家に電話で連絡を入れた。さらに生産者との関係を深めるため、現地に入って農地の現状やコメ作りの苦労など現場を直接自分の目で確かめ、交流も深めていった。
当初は、販売店とはいえ見ず知らずの相手からの連絡に生産者も戸惑ったという。しかし、真一郎が「いいお米で感激しました」と率直に伝えると、生産者も「一生懸命に作っておりましてね」と栽培への思いを返してくれた。そうしたやり取りが、両者の関係性を深めていった。
真一郎が訪ねたのは、奥出雲町など島根県内のコメどころといわれる地域が多かった。その際には、栽培に関するいろいろな気付きを得ることができた。
例えば牛を飼っている農家によるコメ作り。農家は家族のように牛をかわいがり、それと同じようにコメ栽培も丁寧で、コメの品質の高さにつながっていた。真一郎は「おいしいコメができる理由が、現地に行くことで良く分かった」と振り返る。
30年後も店の看板商品
訪ね歩いた先の一つで、真一郎が注目したのが奥出雲町馬木地区だった。店で仕入れたコメの品質を独自にチェックし点数を付けていたが、品質の高い順にみていくと同地区のコメが多くを占めており、馬木地区へと向かう衝動に駆られた。
同地区に足を踏み入れると標高が高く、寒暖差があることが品質の高いコメにつながっていることが分かった。「何としてもこのコメを消費者に届けたい」との思いがわき、仕入れコストが高額になることは覚悟の上で、同地区のコメを集めることを卸業者に依頼した。
仕入れた同地区のコメは、平成元年ごろに仁多米コシヒカリ「まき」として販売を始めた。まきは消費者の人気を集め、約30年が経過した現在でも店の看板商品の一つとなっている。
さらに消費者に受け入れられる上質なコメの販売を目指した真一郎は、自ら音頭を取って1989(平成元)年に県内の6人の農家でつくる仁多有機研究会を発足させた。栽培方法や堆肥使用などに関する農法を統一し、商標登録を取って販売を始めた。
幼心に産地での記憶
県内の産地巡りや仁多有機研究会での取り組みで、生産者との強いつながりを持ったことは、人としても商売人としてもかけがえのない財産となった。
真一郎は「食糧管理法の中で、いいお米があっても、買い付けることができない時代だった。でも、そんなものはいつまでも続かないと思っていた。産地巡りなどのこうした取り組みで一番良かったことは生産者に近づけたことだ」と強調。生産者と販売者が一緒になって県産米を育て高めていくことの必要性を感じ取った。
産地巡りには、当時園児だった長男で現社長の真由(37)を連れて行くことがあった。雨が降り出しそうになると、道路に小さなカエルが次々に現れることにはしゃいでいた真由。幼心に産地を巡った記憶をとどめており、20年ほどの時を経て2008(同20)年に藤本米穀店に入社すると、こだわりの米を販売する父親・真一郎の思いを引き継いでいった。